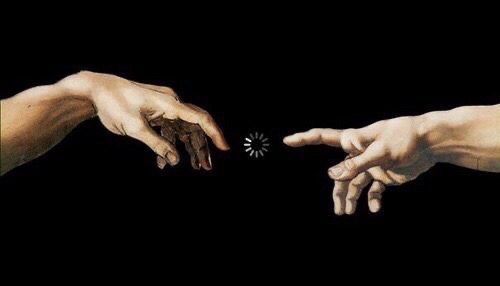最後にまだ、あなたのうちに神を探し求める道がある。すなわち、かぎられているものどもの除去の道がある。というのは、芸術家が木の魂のなかに王の顔を求める場合、
その御顔のために全てを捨て去るからである。
ニコラス・クザーヌス
De quaerendo Deum49
「はじめに」
日本において太宰治の「人間の格」を語るとなると良い印象を持たれない。2021年現在、小林秀雄、柳田国男等の昭和の知の巨人と呼ばれる人と並ぶと、地位は高いのか低いのか、それさえも彼は定まらない。「有名」という地位であることは確かである。恐らく海外の人から見れば「文豪」であるだろうし、日本でも「文豪」ではあるが、彼は嫌われることも多い。ただ、私が太宰治を好むのは、私が太宰治を好むのは、単に話が素晴らしいからという理由ではない。三島由紀夫や谷崎純一郎等の作家を語ると、読書家が煩い。例えば、谷崎潤一郎作品の関西弁を下手に朗読した途端、「けったいな関西弁で不快やわ」と言われてしまう。それに比べて太宰治ファンは太宰の死にざまのせいか、徳が高くなかったせいか太宰を多少ミスリードしても批判されることは少ない。これほど穴場の作家はないと私は思っている。太宰文庫は夏に売れると聞くが、今でもそのようだ。彼の口語調の文体に重々たる文豪に備わっている理知的なものは存在しないと言う人もいる。当たり前に存在しているものを感性豊かな文章で書いたことは、宗教的にも哲学的にも問題提起と成り得る。そして、彼の感性というのは、国語辞書にしか載っていない特別な言葉が飾られるような技巧ではなく、極めて日常的に使われる言葉の羅列が多いことも特徴である。
二人の女性から見た太宰
太宰と関わった女性や著名人は他にも大勢いるが特に私が思う接点が深かった二人を軽く紹介する。
山崎富栄
「死ぬ気で恋愛してみないか」と太宰治に口説かれた心中相手。太宰は学生時代にも心中事件を起こしているが、
それとは別である。学生時代の心中事件の死んだ女性について太宰は「人間失格」以外にも「道化の華」や他の作品に何度も書かれてある。太宰の結核の看病に必死、愛情を独り占めするために必死にらなければならない、と彼女はナイチンゲールのように太宰の看病をし続けた。富栄は太宰が戦後の変わりゆく日本人に対して苦悩しているということを知り、女が大きなものに巻かれて生きることしかない事を盲目に受け入れていたことに自覚する。冨栄は戦時中に、家族に行き遅れを恐れられ結婚し、その夫がフィリピンのマニラで帰らぬ人となった。彼女は未亡人となった。「所帯くずし」という言葉が存在する日本、当時の彼女の孤独を癒せるものはいなかった。富栄と太宰の心中後に、父親は娘の孤独を理解してやればよかったと後悔を残している。彼女は契約結婚とはいえ純粋にマニラに行った夫を愛していた。太宰は世間とは違い、昭和22年、6月3日に脱稿した「フォスフォレッセンス」で架空の花、phosphorescence(燐光を発すること)を中心に冨栄への愛と、夫への招魂祭を描いている。戦死した夫への愛情を何処へやったら良かったのか、富栄の鬱屈した気持ちを世間は許さなかったが、太宰だけが許し、夫への愛情も受け入れてくれた。「人間失格」は太宰治の遺作であり、冨栄が太宰を看病する中執筆された半自伝と言われている。
遺族が娘、富栄の風評被害を止めたいと日記を出版。
津島 美知子
太宰治の妻で、夫の繰り返す不貞と我儘の中耐え抜いた。心中相手の山崎富栄の描写する太宰とは一転、そこには夫失格、暴君の太宰治が書かれてあった。太宰が「駆け込み訴え」を蜘蛛が糸を吐くように読み上げるのを書き上げただけあって文章が聡明。太宰治の文章が感傷的なら、妻の津島美知子の文章は理知的である。太宰の執筆世界の「妻」は文章が美しくない、と女として落ちぶれている女が書かれているが、現実の奥さんの文章は女としても柔らかく美しいさながら、太宰という困った夫と世間を静観している。「女生徒」は実際の若い女性の愛読者の日記に拠っている。これは「斜陽」のモデルとなった太田静子の例もあり、妻の日記には太宰にはそういった依頼が多かったようだ。女生徒の「胸のところに、小さい白い薔薇の花を詩集して置いた」というのを太宰は「赤い刺繍」と書いていた。これを「白」と言ったのは妻だそうだ。カトリックに属している私としてはこの中で誰よりも妻である津島美知子の献身的であり、夫婦、家族としての要を一人で守り、富栄よりも妻の努力を肯定せざるを得ない。この価値を理解したのは私も最近である。それだけ、家族の意味を理解するのには時間がかかるのだ。個人的な感想になるが、愛は何が素晴らしいと決定づけられないが、辛さや耐え抜いた先にもあるものだなと思わせた。愛という言葉すら陳腐になってしまうほどのものがあった。
「人間失格と太宰治」(感想)
主人公の葉蔵は幼少期から美少年だったが、幸福というものへの思索に帰結出来ず、疑問を持っていた。彼の内部を覆う外皮、人々は彼を「仕合せ」と判断する。その言葉は何処か表面的で主人公の心には響かない。そして彼を取り巻く世界が日本の優等生かの如く、彼のような悩みを持つ者が見当たらない。主人公は世間に対して、彼等を「夜はぐっすり眠り、朝は爽快なのかしら」と思いに耽る。そして、見落とされるほどの少ない描写であるが葉蔵は子供のころに、下人に「悪戯」(性行為)されている。彼は両親に被害を訴えようとは思ったが、人間の落ちぶれている様、本質を眺めることに快感を得ていた。「道化の華」や他の作品でもこの人間失格の内容は多々見られることから、太宰は「人間失格」を書くために作家になったと定評がある。日本語という「品性」によって書かれてあるが、出来事だけを並べると仏教でいえば「人間の業」そのものである。言葉(センス)が人の中に住む「獣」を隠している、その緊張がこの作品は「道化の華」と比べて秀逸である。
葉蔵は繊細で、人間の本質を眺めることに快感を得ていた。日陰の人間に優しさを与えて、彼女らが感謝することによって自分が善人になれたような気がして酔っていた。そんな葉蔵は他郷の学校へと通うことになる。実家が最もやりにくい場所(演じにくい場所)だと彼は言っている。「道化」として周囲と調和を取って心の中を悟られないようにする。そんな中鉄棒から落ちた葉蔵を、見学していた竹一に「ワザ ワザ」(わざと)と見抜かれてしまう。葉蔵は竹一を殺したいと思うものの、それは本心ではないと思い直す。むしろ殺されたいのは自分だと意識が揺らめいていた。葉蔵は竹一を取り込んで彼の家へと行く。竹一は耳を悪くしていたので、葉蔵は彼の耳を掃除してあげると偽善の計画を立てた。すると竹一は第一の預言を葉蔵にする。
「お前は、きっと、女に惚れられるよ」
それは愛されるよ、というものではなく「惚れられる」ということだった。それがどう違うのか、好かれるというより「かまわれる」という事が如何に甘美な誘惑で不幸を招くのか彼は既に知っていた。竹一の姉妹もまた葉蔵に惚れているようだった。しかし、この時はまだ序章に過ぎなかった。竹一との交流がきっかけで、葉蔵は絵を描いてみるが、絵を描いたときに道化の自分とは正反対な陰惨な絵が仕上がった。それを見て、彼はその絵こそ自分の正体だと知るのだった。それによって「お前は、偉い絵描きになるよ」と竹一から第二の予言をされる。第二の手記の終盤は、太宰の繰り返される過去でもある「情死」事件である。葉蔵はツネ子という女と鎌倉の海に飛び込んだ。女だけは死んで、葉蔵は自殺ほう助罪で連行され、起訴猶予となった。
第三の手記の始まりで、竹一は第一の予言は当てたが、第二の予言は当てなかったようだと始まる。ここまでの流れだと、ヘッセのアウグストゥスとも似ている。アウグストゥスもまた美形で皆が彼を愛した。それによって、アウグストゥスは人を愛することを覚えず、人に酷いことをするまでになった。母親の死をきっかけに、彼は与えられた魔力であった愛されることを手放したいと懇願した。それによって彼は誰にも愛されずに、今までの行いの償いとして刑務所へ入れられる。ヘッセはキリスト教学校を抜け出したと言っても、アウグストゥスはキリスト教圏の価値観が根付いている。それは「惚れられる」というものを神の恩寵とせず「魔術」としているからである。それは宗教的な異端の魔術ではなく、メルヒェンとしてのものである。しかし、魔術だからこそ彼は手放すことが出来た。そこから彼は誰からも愛されず、嫌われながら人を愛した。マタイの福音書の5章の「心貧しい者は幸いなる」を体現するのである。
ヘッセも太宰と同じく自殺未遂をしている。共通項として彼等は二人とも聖書は愛読していたことである。特に太宰治は不倫相手の太田静子に会いに行くときも聖書を持って歩いていた。妻の回想録でも夫、太宰治は聖書を持っていたことを残している。心中相手の山崎富栄もYWCAでキリスト教とフランス語を学んだ。師匠は小林秀雄の実の妹の「高見澤潤子」だった。彼女は聖書を太宰と語り合っている。人格の違いは当然だが、ヘッセと太宰治、この分岐点は日本人の嵯峨を背負っている、と私は思わずにいられない。それは大衆キリスト教が声を張り上げる「恋と愛の違い」とは違う。多くの人が恋と愛を区別をし、愛のほうが素晴らしいと思い込んでいる。本当はそうではない。
「愛」でも「恋」でも大差ないことであり芽が出て花となり実のなる過程でしかない。大切なのは、イエスの愛を理解しながら、「贖罪」することだ。それこそアウグストゥスのように、身を粉にしなければならないこともある。それが真のキリスト信徒と、無宗教の違いである。「人間失格」の葉蔵は隣人を理解出来ないままだったが、隣人の幸福が気になって仕方なかった。人間に対して興味が持てない男の求愛は「道化」となる。父母の前でも溶け込めない葉蔵は成長するにつれて、孤独の香りが魅惑となり、女性たちに嗅ぎ当てられる。そして、彼は女性たちの秘密を守る色魔となっていく。葉蔵はバア(酒場)で飲んでいる葉蔵を止める十七歳のヨシちゃんと結婚する。彼は漸く分別のある男になり、友人の堀木と「喜劇名詞」「悲劇名詞」と感覚で云い合って酔っていた。罪の対語は「蜜」だと言った後に、妻であるヨシちゃんが下の階で他の男と不貞をしている姿を見てしまう。
ヨシ子は、信頼の天才。そうまで思っていた女性から裏切られていても、友人である堀木は葉蔵の生い立ちを知っているせいか、
「ゆるしてやれ お前だって、どうせ、ろくな奴じゃないんだから」と言ったのである。
相手の男は葉蔵に漫画を描かせている商人だった。
葉蔵は妻が他の男と情事を重ねる本を読み漁っては、妻の秘め事であった堀木に恨みを募らせ、彼は妻との向き合い方を失っていた。「無垢なる信頼心は罪なりや」とは、聖母マリア(処女性)のように純粋だと信じ切っていた男ヨセフへの問いでもあるだろう。それは第一の手記に書かれてあった「人間への不信は必ずしもすぐに宗教の道に通じているとは限らないと、自分には思われるのですけど」「人間は、お互いの不信の中で、エホバも何も念頭に置かず、平気で生きているではありませんか」「しかし、こんなのは、ほんのささやかな一例にすぎません。互いにあざむき合って、しかもいずれも不思議に何の傷もつかず、あざむきあっている事にさえ気がついていないみたいな、実にあざやかな、それこそ清く明るくほがらかな不信の例が、人間の生活に充満しているように思われます」という聖書物語は現実と乖離することと繋がっている。
聖書を愛読しておきながら、太宰が描く葉蔵は「隣人を愛せ」である隣人の幸福が気になって仕方ないだけでなく愛し方を漸く覚えたと思えば妻に裏切られる。言葉では妻を許すと言いながら、友人を恨み、恨んだかと思えば考えが飽和する。葉蔵はより年齢に反して見た目が老いていく。今年27歳になります。白髪がめっきり増えたので、たいていの人から四十以上に見られます」というのは、これは太宰自身が40代でありながら、実際に起こしてしまった心中事件で女性だけを死なせた事への想いが込められていると思う。(実際にあるウェルナー症候群とは別として、これは心理的に寄せた一行だと全体を通して判断する)
心とは、何かもっと核があるものとして当然のごとく常に自分のところに存在しているものだと思いたい。それなのに
一向に心というものが感情として力を見せるのは「運次第」なところがある。その上、全くその思考過程が分からないという人も存在する。心と自分が離れていくような浮遊感、これを病気とするのなら解離症というが太宰には双極性障害の他に解離症もあったと推測される。幼少期の大人からへの性的暴行が事実だとするのなら、それはPTSDの影響であったのではないか。解離症は幸い、病気でありながらフランスやドイツ哲学や文学として混ざってもいたので、うまく使えば白痴から免れるところがあった。「主観」「客観」「現象」「存在」「意識」ここに疑問を持ち始めることは学問でもあった。シェークスピアの「ハムレット」のオフィーリアが狂いながらも、兄が「狂人にも教訓があるとでもいうようなものだ」と彼女の散文詩は何処か意味があるように思えてしまった。オフィーリアも狂いながらも「イエスキリスト」の名は外さなかった。
Well, God yield you! They say the owl was a baker’s daughter. Lord, we know what we are, but know not what we may be. God be at your table.
――ありがとう、God yield you! フクロウは元々はパン屋の娘、イエスから罰で姿を変えられたの。でもわたくしは違うのよ、こんな姿になってしまったのは。ねぇ、王様。私達は先のことは分かることは出来ないのよ、God be at your table.
–Ophelia
A document in madness, thought and remenbrance fitted.
――侠気にも教訓があるというものか、物を思っても忘れるなとでも言うようだな――
–Laertes
ハムレットの悲劇も人殺しの「贖罪」をしなかったことにある。これは日本文学より明確である。但し、それでも物語によって人は宗教以外の「教訓」を得てしまう。人間を知るための鏡として、人間模様の再現の舞台のように。それが文学の誘惑でもある。G・バタイユは「文学と悪」を研究するほど、清廉潔白な生活と現代文学は相性が悪い。何故ならその「悪」「弱さ」を残すことによって時に人の精神を救うからである。人間は思惑だけでは意識にはなれない。誰かの言葉によって意識化するのである。知らない誰かの言葉が、自分を形成する。より人間を知ること、それを担う文学というものは錬金術のように自分が毒に侵されながらも抽出することさえある。想像だけで書いた「愛」は大衆の想像力に当てはめやすい。人々の共通認識がその話を理解できるからである。
しかし、個性的な拗れた人生を送った作家が書いた愛の話は共感を得にくい。人の想像力では追い付かないからである。それと、イエスの磔刑の全人類を許した「愛」とは何が違うのか、それこそ「聖と俗」である。作家は自分たちが「俗」であることを自覚しなければならない。ダンテの「神曲」は今だからこそ神聖な扱いであるが当時はダンテは国外追放されたのだ。無実の文豪を私は知らない。聖と切り離してしまうことも出来ない、そのもがき苦しむことが意味があるからである。
芸術的感性は「自由の刑」に処されている、私はそう思っていた。それが20世紀以降ではないだろうか。特にサルトルの自由の刑を知る前から、子供ながらに「自由、自由、と言いながら、目に見えない世間に感謝しなければならない拷問だ」と思っていた。自分にとって神も「世間」も目に見えないものと同列だった。音感や色感、それが他人より敏感なこと、言葉で意識を噛み砕くのが他の人よりも繊細であること、それらは自由と言われながら、そうではない。その抱えた感情をどうしたらいいのか、誰も教えることは出来ない。どうしたらいいのか、藻掻いて探す他なかった。プラトンのイデアという「美」という理想があるとすれば、対義語は「現象」であるだろう。そしてもっと現象は哲学言語や芸術感性にとって美しい皮を被ることがあるが、無自覚に「人間失格」で有名な「それは世間が許さない」の「世間」にもなる。「世間というのは、君じゃないか」太宰は、見事に文学として宗教や哲学用語に依拠せずに適格な言葉を残したように思う。それだけで私は太宰に脱帽している。
更に、「世間が許さないのではなく貴方」と世間という他人を装う名もなき人を彼はしっかりと掴んだ。それは「貴方」なんだと、世間という大きなものの影にかくれる卑怯な人格を彼は掴んだ。世間から削り取られていく自我と、当時の訳ありの女性たちは似ていたのかもしれない。女性は特に若ければ独身、次に家庭の中にいなければ人権が無いようなものだった。未亡人となれば、結婚を手段としてまた儀式的な再婚が待っている。川端康成を始め、彼を酷評する専門家は大勢いたが、彼を肯定してくれる女性たちによって、彼は生き始める。「人間失格」の葉蔵はその一人だろう。
存在を定義つけるものは、頭の中だけなのか。それとも「世間」か戸籍か、全ての理知的な哲学、神学を一蹴するものは何か、エロスとタナトスが抱擁した時である。エゴン・シーレの「死と乙女」にはエロスに生きようという衝動と安定的に生きたいというシーレの卑怯な人間性が死神に現れている。これも一つのシーレの「人間失格」だろう。遠目で見ていると、抱擁によって一蓮托生のようにも見えてしまう。けれども細部を見てみると、女はしっかりと死神を抱いているが、死神は女性の肩に手をかけている。この遠目では気づけない力加減は「人間失格」である。シーレの美は、宗教絵画のような美ではない。人間にとって神の光も目に見えないが、醜さも同等に隠すからである。人はどちらも見つけるとその存在に恍惚になる。だから神の光と人間模様は常に聖と俗を切り離せずに人々の芸術となってきた。
 エゴン・シーレ「死と乙女」
エゴン・シーレ「死と乙女」
シーレが十代をモデルにして逮捕され、教会との対立があった。私が十代の頃には自分自身がモデルになって好きに描けた。自画像は顔だけとは限らない。早くうまくなるには自分をモデルにすることだと教えてもらったので、私は自分の裸体を描き続けた。昔の人にとっての斬新さは現代において無意味になっていた。当時の自分にとって未経験なのは「愛」だけだった。中世の画家が人間の解剖をして人間を知ろうとしたことを、崇拝するような教えが多く、それが退屈で仕方なかった。文明と進化、それで私達は有難いと思うらしい。それは葉蔵の「空腹がわからない」というのと当時は重ねていた。若い頃に読む文学というのは体験と経験が足りているわけでもないので、想像によって、もしくは脳が錯覚して類似点で認識していく。それが他人から見れば、「全く違う」と言われることになっても、そうやって物事を認知していく他なかった。何故当たり前の「空腹」で人は言葉にするのか?というのと、当たり前に裸体ぐらい見れるのに、エロスをがキリスト教から離れたことについて斬新なアイディアのように現代美術は言うのか、それをよく重ねていた。いつしか、裸体、骨格を私の指先は覚えたようで、様々な想像上の人物を描いた。成人ヌードはいつでも手に入る。風俗に行けば、女でも陰部を簡単に見せてくれる。絵を描き始めたきっかけは、子供のころに色彩感覚が褒められたからだった。他の理由は忘我したように時間が過ぎて、自分の指で何かを成し遂げる、自分の小世界を作ることは楽しかった。ただ起きて、似たような毎日を過ごす中で、哲学的なことや、神を考えること、それを「表現」することによって何処かで世界の真理と繋がることがあるのか、それを夢見ながら書き続けた。プラトンの「イデア」のようにいつも何かを見つけられることを探していた。それは美しいものなのか、結局のところ探したいのは「自分」でもあった。否、今の自分を認められない自分が、新たな自分を作ろうとしていた、それが一番強いのだろう。しかし幼いというのは過去に何かあるのか、というほど過去が揃っていない。過去の温存がまだ中途半端だからだ。だから、未来への自分、新しい自分を作れることを期待する。それが私の若さだった。作品賞の批評で大人がバカにしたように「自分探しの作品は稚拙そのものだ」とよく言っていた。恐らく何点もの作品に見せられる「自我への問い」に飽き飽きしていたのだろう。そういう人は太宰治も決まって嫌い、太宰の批判をする。太宰は絵描きではなかったが、こういう場でも例として出てきてしまう。しかも悪い例として出てきてしまう、それほどの存在だということは凄いことかもしれない。
けれどもそういう人に限ってエゴン・シーレは褒める。教会との対立が日本人にとっては自我を貫いているように見えるようで、尊敬しているそうだ。話を聞きながら似てるようなものなのに、と私は心の中で笑った。私はこの当時、「人間失格」の内容の趣旨は分からなかったが、睡眠薬のカルモチンと下剤のヘノモチンを間違えて笑う心境を独自に重ねていた。きっとこの人は二人ともよく知らなくて、大恥をかくことも知らずに取り違えているのだと。私はこの時はこれが「喜劇名詞」なのかどうかまで分からなかった。喜劇とは滑稽な人間の様を笑う、本来は人間の哀しみである。この語りは所謂、私の思い出話で経験が違う人は「それは違う」という人も出てきたとしても、突き切る感情があること、自分の経験を書き尽くすこと、それが創造性にとって重要だということは確かだろう。カルモチンーヘノモチン、真面目な人はカタカナを読み間違えるほど主人公の病気が悪化したと思う。少し感性的に答えるのなら、下剤は食べたものの結末を速めるだけだと答える。結果としてくることを安易に早めてしまうことは良いこととは限らない。それは、冒頭の空腹というものが分からないという話とつなげることが出来る。食と下剤、肉体としては「空腹」状態である。身体はそうなったが、主人公は時間の無常に目を向けている。どうせ訪れる運命を速めることがどんな苦しみを持つのか、例えば「死期」もそうだ。舞台を司る神は、それすらも計画だとする。一切過ぎていく月日の出来事が、作者が経験を何度も噛み砕いて虚構となって、後に外せない必要な柱の一本になってしまったのはいつなのか?
それこそ舞台芸術の問いになりそうだが、彼には津島修二という本名があるが、その本名としての人格が殆ど残っていない。妻ですらも主人を「太宰」という名前で回想録に残していた。
私のように信仰がある者にとっては、虚構世界の中は守られていると思う。太宰である津島修二は家族や妻にとって、そしてイエス・キリストを裏切っている。彼が書いた「駆け込み訴え」のように、イエスを愛しながら裏切っていた。但し、彼等の行いは洗礼を受けてはいないので裏切っているとまで言えるかどうか定かではないが、殺人に近いので戒律は既に犯している。しかし太宰の分身、葉蔵は永遠に咎められることがない。「芸術家とは孤独」とは、アマチュア芸術家にとって甘美な言葉で、破天荒な行いで孤独になる、孤高な存在で孤独になると思い込んでいたようだが、ここで私の裸体の話に繋がる。本当の孤独とは神を裏切ることである。それでも書かなければならないという衝動が、悪魔的なのか啓示なのか不明なことが痛みである。
本来の教会法に基づいた「赦し」であるのなら、信徒は「罪の告白」によって孤立を防ぐ。けれども、虚構世界と繋がってしまった罪は「罪の告白」をすることが出来ない。許されてしまった後、どんな作品になってしまうのか怖いからだ。今にも罪を打ち明けたいと思っていたとしても、この混乱が、葛藤が執筆を勧めるのなら、神父には語れない。文学には「毒」が必要だからである。役者にも、役に入らず台詞だけで仕事をこなせる役者と、役に感情移入して成り済まして演じる役者もいる。太宰は、一番精神を混乱しかねない後者だったように思う。文学としての評価はこの作品の場合は、葉蔵は作者「太宰治」の人生の入り口を開けてしまっている。だから、他の作家の作品は作品と作者を切り離すことに成功できても、彼の場合は出来ないのである。
作中にあったように、そして彼等の人生を通してあるように、幾ら聖書を読んで感動したところで、イエスキリストと無関係で私達は生きていると思うほど、日本の生活はキリスト教とは離れている。妄信以外は皆、同じ体感だろう。それは「愛」のみでしか考えないからだ。愛に痛みが伴うこと、信徒の義務として「贖罪」と「許し」がある。これらを通して私達はイエスと繋がっていく。贖罪と許しから逃げ続けた恋慕、この業という業を自覚し、ここまで鮮明に残せたことは私は評価している。だから、私は太宰治の本は本棚に残している。キリスト教徒としてそれは自分は清廉潔白だと区別していまうこと、これが一番の妄信だと思うからだ。
言葉で多様性は表現出来ない。それなのに理解されるか不確かな感情を書くことは報われないことが多い。大半は人の共通認識に合わせて言葉を選ばなければならない。彼等のように刹那に生きること、彼は世間の道化であり、彼の隠れなかった闇は人の精神に触れてくる。彼の作品の言葉は単純な愛の言葉のようで、芯が無いように見られるが、その単純な言葉を熱を込めて言ってくれること、ロマンは生きる上で重要な力になることを惜しみなく書いている。
「人間、失格」
もはや、自分は、完全に、人間で無くなりました。
この剪定されて落ちた枝のような言葉を私は何度も繰り返し読んだ。年齢ごとや気分によって感想は変わっていたが、「世間」から切り離された枝、その哀しみにイエスはいる。神は農夫でイエスは葡萄の木という話がある。(ヨハネの福音書15章)剪定とは、要らない存在を斬ることではなく、幹であるイエスも悲しんでいるという意味であり、「命の繋がり」を表している。剪定した後の木は樹液を出す。それをイエスの涙と例えられる。
剪定された枝の一つのように、時が過ぎ去るのを傍観する。それがこの作中の主人公であり、文学者の肉声だろう。私はこの孤立が遠い存在のように思えなかった。長らく私はキリスト教圏の文学は神と共に残っているが、日本文学は死と一緒に残すものだと信じていた。それほど過去の日本文豪はタナトスが多い。肉体の死と他に、精神の瀕死が存在すると昔から疑わなかったのと、それを何故か捨てたいとは思わなかった。この死の美学が分からない国の人になりたくない、とすら思っていた。タナトスとは幸福や不幸とまた別の美学であって、それによって生きたいのである。時々、取り込まれながら、抜け出しながら、再起を賭けたり絶望したりを繰り返して、「生」を感じていたいのである。
剪定された枝は無抵抗で無常を見つめること、「人間失格」は「世間」というものについて、嘘は書かなかった。彼の言葉には偽善がないのである。学生時代に鎌倉の海で死なせてしまった心中相手の女性について書き続けた彼は、何度も自分の罪とは向き合っていたように思う。一人の自殺未遂と、愛した人を巻き込んだ自殺はまた違う。
法律では償えなった罪、大半の人間は罪の自覚の仕方すら知らないように思う。太宰もまたそのように苦しんでいたように感じ取れる。一生、償えない苦しみを自覚したら背負うことは恐ろしいだろう。イエスを裏切ったユダが自殺をしたのを思い出してほしい。イエスキリストが十字架を背負った事が如何に重要だったのかが分かる。
人の不完全さを見つめる力がなければ宗教も文学も成り立たないのは同じである。自覚によってイエスと繋がることは「贖罪」と「赦し」であるが、常に意識していないところに神がいるのも真意である。太宰と女性の与えられた生涯に、自死という選択があったことに、神も泣いているということを忘れてはならない。この世界、神(愛)が泣かないとするのなら、第三者の死を愛をもって誰が泣くのだろうか。
太宰治の「人間失格」は特に読みながら自分を見てしまう。太宰作品でなくても話を読むというのは、皆、自分を見つめている。大半の読者は自分の死生観、恋愛観を見てしまうので、容易に葉蔵に辿り着かない。下人に悪戯された、妻が不倫された等を直接的に書いていないがために短編でありながらミスリードが多い作品だと思う。
最後の葉蔵が「廃人」になったことについて、それは目に見えないものを追いかけた者の末路なのかもしれない。聖なる自分と、罪深い自分は常に共存する。罪深さが深い森へと案内とし、クザーヌス神学のように神が映る木を探す。そのために全てを捨て去るというのは、言葉だけではどうにもならない。私は道徳的に立派だった小説家を傍に置かない。私が選ぶのは「世間」から剪定された枝のような存在ばかりだ。特に最近はそうしている傍に置く。聖書と弱いもの、その相対性を持つことはキリスト者にとって、それは「手鏡」ではないだろうか。
愛や死に抱く想いは、上昇と下降を繰り返す。単純な言い回しの裏で、あの頃よりも音と思惑が深く響きながら何処かへ届くように、希っている。
再起:悪い状態から立ち直ること
ヨハネの福音書15章(1~12)
わたしはまことのぶどうの木、わたしの父は農夫である。
わたしにつながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれをとりのぞき、実を結ぶものは、もっと豊かに実らせるために、手入れしてこれをきれいになさるのである。
あなたがたは、わたしが語った言葉によって既にきよくされている。 わたしにつながっていなさい。そうすれば、わたしはあなたがたとつながっていよう。枝がぶどうの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなたがたもわたしにつながっていなければ実を結ぶことができない。 わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。もし人がわたしにつながっており、またわたしがその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。わたしから離れては、あなたがたは何一つできないからである。 人がわたしにつながっていないならば、枝のように外に投げすてられて枯れる。人々はそれをかき集め、火に投げ入れて、焼いてしまうのである。 あなたがたがわたしにつながっており、わたしの言葉があなたがたにとどまっているならば、なんでも望むものを求めるがよい。そうすれば、与えられるであろう。 あなたがたが実を豊かに結び、そしてわたしの弟子となるならば、それによって、わたしの父は栄光をお受けになるであろう。 父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛したのである。わたしの愛のうちにいなさい。 もしわたしのいましめを守るならば、あなたがたはわたしの愛のうちにおるのである。それはわたしがわたしの父のいましめを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。 わたしがこれらのことを話したのは、わたしの喜びがあなたがたのうちにも宿るため、また、あなたがたの喜びが満ちあふれるためである。わたしのいましめは、これである。わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互に愛し合いなさい。